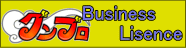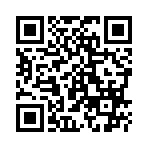2008年12月14日
家の家相
家の家相・・・
新築をするときや、リフォームで間取りを変更するときは気にされる方はいます。
私自身も、悩むところがあります。

鬼門に当たる場所にトイレなどの水廻りは置かない、
廊下の突き当りのトイレは凶
夫婦寝室は北西が良いなど・・・
そこで多くの制約が生まれてしまいます。
お客様の要望であれば、それに基づいてプランニングをすることが私の役目ですが
特に要望がなかったり、全く気にしないのであれば
どちらかというと、家相は気にしないでプランニングはしたい方です。
先日、家相を調べていると興味深い話がありました。
家相は気学や風水に通じる開運学の一つであります。
中国で誕生したその思想は江戸時代に日本に入ってきました。
家相はその江戸時代の家の間取りに当てはめて考えられたとも言われています。
そこで一つの矛盾が・・・
江戸時代の住宅と、現代の住宅ではその根本的な間取りが違います。
確かに、現代の住宅では生活のすべてが一つの家の中で完結できますが
江戸時代の住宅を見ると、トイレや風呂などは家の離れに置かれる形でした。
つまりは、今の住宅ではトイレや風呂の位置を動かすことは、その他の動線を考えても
間取りを変更しなければなりませんし、間取りの制約がそこで生まれてしまいます。
一方、江戸時代の住宅の形態では、風呂やトイレが離れにあることは、
その位置を変更したところで、間取りの制約はありません。
自在に動かすことができるのです。
このことは家相として何か変化はあるのか・・・
そして、もうひとつ・・・
家相学の文献とも言われる書がいくつかあるのですが、
それらには、統一性がないということに気づきます。
それぞれの文献がそれぞれの吉凶があります。
それでは、何が正しいのかはわかりません。
家相は単に迷信の事に過ぎないのか・・・
更に・・・その興味深い話はこう締めくくられています。
「住宅の間取りを決める時に家相を過信しすぎることは
かえって、住みづらい間取りを形成してしまう。
それが、家相を信じるゆえの吉の出来事であろうか。
住みづらいということは、厄以外の何物でもないと感じる」

私自身もそれが確かな考え方だとどうしても感じてしまう。
そして、もし家相をきちんととらえるのならば、良い考え方もできます。
なぜ、鬼門は水廻りを避けるのかというと
水廻りはつい汚くなりがちだからなのです。
不浄なものを鬼門に置かないという考え方であるならば、
水廻りを鬼門においても、常にきれいにしておけば全く問題はないととらえることもできます。
つまりは、家に住む人の普段の生活や、家に対する考え方さえしっかりと持ち、
どの部屋もしっかりと綺麗にしておけば、厄など起こるはずがない。
私は家相を考える上で、そのような考え方にたどり着きました。
問題はそこに住む人とそれを作る人の想いをお互いに感じることができることが大切なのです。
増改築の事ならアールプランへ・・・
ホームページはこちらへ・・・
新築をするときや、リフォームで間取りを変更するときは気にされる方はいます。
私自身も、悩むところがあります。

鬼門に当たる場所にトイレなどの水廻りは置かない、
廊下の突き当りのトイレは凶
夫婦寝室は北西が良いなど・・・
そこで多くの制約が生まれてしまいます。
お客様の要望であれば、それに基づいてプランニングをすることが私の役目ですが
特に要望がなかったり、全く気にしないのであれば
どちらかというと、家相は気にしないでプランニングはしたい方です。
先日、家相を調べていると興味深い話がありました。
家相は気学や風水に通じる開運学の一つであります。
中国で誕生したその思想は江戸時代に日本に入ってきました。
家相はその江戸時代の家の間取りに当てはめて考えられたとも言われています。
そこで一つの矛盾が・・・
江戸時代の住宅と、現代の住宅ではその根本的な間取りが違います。
確かに、現代の住宅では生活のすべてが一つの家の中で完結できますが
江戸時代の住宅を見ると、トイレや風呂などは家の離れに置かれる形でした。
つまりは、今の住宅ではトイレや風呂の位置を動かすことは、その他の動線を考えても
間取りを変更しなければなりませんし、間取りの制約がそこで生まれてしまいます。
一方、江戸時代の住宅の形態では、風呂やトイレが離れにあることは、
その位置を変更したところで、間取りの制約はありません。
自在に動かすことができるのです。
このことは家相として何か変化はあるのか・・・
そして、もうひとつ・・・
家相学の文献とも言われる書がいくつかあるのですが、
それらには、統一性がないということに気づきます。
それぞれの文献がそれぞれの吉凶があります。
それでは、何が正しいのかはわかりません。
家相は単に迷信の事に過ぎないのか・・・
更に・・・その興味深い話はこう締めくくられています。
「住宅の間取りを決める時に家相を過信しすぎることは
かえって、住みづらい間取りを形成してしまう。
それが、家相を信じるゆえの吉の出来事であろうか。
住みづらいということは、厄以外の何物でもないと感じる」

私自身もそれが確かな考え方だとどうしても感じてしまう。
そして、もし家相をきちんととらえるのならば、良い考え方もできます。
なぜ、鬼門は水廻りを避けるのかというと
水廻りはつい汚くなりがちだからなのです。
不浄なものを鬼門に置かないという考え方であるならば、
水廻りを鬼門においても、常にきれいにしておけば全く問題はないととらえることもできます。
つまりは、家に住む人の普段の生活や、家に対する考え方さえしっかりと持ち、
どの部屋もしっかりと綺麗にしておけば、厄など起こるはずがない。
私は家相を考える上で、そのような考え方にたどり着きました。
問題はそこに住む人とそれを作る人の想いをお互いに感じることができることが大切なのです。
増改築の事ならアールプランへ・・・
ホームページはこちらへ・・・
2008年12月14日
2008年ベストセレクト・・・エクステリア編
2008年ベストセレクト・・・エクステリア編です。
このエクステリアは、家の門構えを変えるというエクステリアです。
家の風格と、植栽に対して、門が小さいというお客様の悩みがありました。
一見、見栄えのする門構えをお客様は求めていました。

完成後の写真です。
こだわりのテーマは、「松」との調和です。
優雅にそびえる、松に門が調和しなくてはいけません。

工事前の写真です。
確かに、家のバランスや、松のバランス的にも門が見劣りしてしまいます。
もう一つの悩み・・・
それは、門が小さいということからくる問題です。
車椅子の通過に支障をきたすという問題があります。
門の幅が車椅子の通過にギリギリの寸法でした。
しかし、ガレージと松に挟まれた空間という限られたスペースで、それを成し遂げなくてはなりません。
門構えと有効なスペース。
同時に課せられた課題です。
門構えはダイナミックに・・・

門構えの高さを変えました。
以前より30センチほど高くすることで、門構えとしての存在感を強調しました。
以前は大谷石の門でした。
しかし、家の囲いから同じ材質で門まで形成されていたので
門の部分が比較的目立つことがありませんでした。
松竹飾る・・・

優雅にそびえる松・・・
そこに竹のイメージ。
竹に見立てたタイルのイメージ。
イメージは大切ですよね。
竹をイメージしたのは、「和」形の門構えにするためです。
大理石のタイルを積み上げたところに、アクセントでタイルを施工します。
大理石の高級感に、ちょっとした「和」のスリット。
連想できるのは「竹」です。
松と調和する形の天然アートです。
大きな門は、有効寸法を確保する。

門を高く、インパクトをつけることで
存在感をつけます。
その中で、門の幅を広げます。
実際は門袖の部分の寸法が狭くなっているのですが
それを感じさせません。

お客様も大満足でした。
「やっぱり門構えはこうでないといけませんね。
今までは、我慢して使っていたのですが
変えることができて本当に良かったです。」
エクステリア・外構工事の事ならアールプランへ・・・
アールプランホームページはこちらへ・・・
このエクステリアは、家の門構えを変えるというエクステリアです。
家の風格と、植栽に対して、門が小さいというお客様の悩みがありました。
一見、見栄えのする門構えをお客様は求めていました。

完成後の写真です。
こだわりのテーマは、「松」との調和です。
優雅にそびえる、松に門が調和しなくてはいけません。

工事前の写真です。
確かに、家のバランスや、松のバランス的にも門が見劣りしてしまいます。
もう一つの悩み・・・
それは、門が小さいということからくる問題です。
車椅子の通過に支障をきたすという問題があります。
門の幅が車椅子の通過にギリギリの寸法でした。
しかし、ガレージと松に挟まれた空間という限られたスペースで、それを成し遂げなくてはなりません。
門構えと有効なスペース。
同時に課せられた課題です。
門構えはダイナミックに・・・

門構えの高さを変えました。
以前より30センチほど高くすることで、門構えとしての存在感を強調しました。
以前は大谷石の門でした。
しかし、家の囲いから同じ材質で門まで形成されていたので
門の部分が比較的目立つことがありませんでした。
松竹飾る・・・

優雅にそびえる松・・・
そこに竹のイメージ。
竹に見立てたタイルのイメージ。
イメージは大切ですよね。
竹をイメージしたのは、「和」形の門構えにするためです。
大理石のタイルを積み上げたところに、アクセントでタイルを施工します。
大理石の高級感に、ちょっとした「和」のスリット。
連想できるのは「竹」です。
松と調和する形の天然アートです。
大きな門は、有効寸法を確保する。

門を高く、インパクトをつけることで
存在感をつけます。
その中で、門の幅を広げます。
実際は門袖の部分の寸法が狭くなっているのですが
それを感じさせません。

お客様も大満足でした。
「やっぱり門構えはこうでないといけませんね。
今までは、我慢して使っていたのですが
変えることができて本当に良かったです。」
エクステリア・外構工事の事ならアールプランへ・・・
アールプランホームページはこちらへ・・・